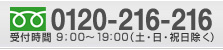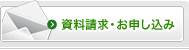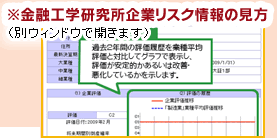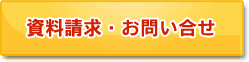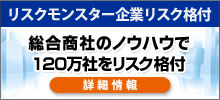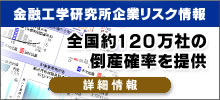米金融危機に 端を発した不況で2008年は新興不動産業の倒産が相次いだが、それに続いて、自動車産業に代表される製造業の景況感悪化が鮮明になってきている(表1参照)。
端を発した不況で2008年は新興不動産業の倒産が相次いだが、それに続いて、自動車産業に代表される製造業の景況感悪化が鮮明になってきている(表1参照)。
エリア別に見ると、自動車産業で潤っていた愛知、静岡の悪化が目立っており、倒産(デフォルト)率が上昇している。ただ両県はもともと倒産率の低い地域であり、倒産率上昇後の水準についても特に高いとはいえない。
また大都市圏の倒産率上昇も特徴といえる。一方、上場企業や大企業をみると、08年下期や09年上期にあったような資金繰り難による黒字企業の"突然死"といった異例の形の上場企業の倒産というのは、金融機関の支えもあってか、ここ2、3カ月沈静化しており、様子を見守っているところだ(表2参照)。
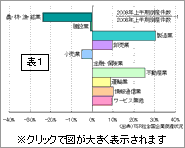
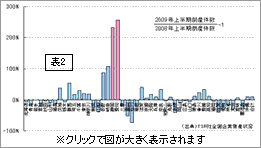
信用リスクの観点から見ると、「成長性が高い」=「信用リスクが低い」とは言えない点に注意が必要だろう。高い成長性と倒産リスクは表裏一体とも言える。身の丈を超えた高い成長性の裏には、高いリスクをとっている可能性がある。したがって、信用リスクという観点からは成長性がプラスであるということだけでは素直に喜べない。成長の結果として財務内容が改善すれば、リスクの低下要因として評価できる。
教科書的なコメントになってしまうが、成長はリスクを評価する直接的な要因では無く、間接的な要因である。そして、企業が抱えているリスクを軽減する成長が、その企業にとって望ましい成長の内容と言える。
そうした点をしっかり区別していくためには、企業規模という要素が重要になってくる。
大企業の場合の高成長と中小企業の高成長では評価が異なる。中小企業の場合、伸びている企業にありがちなのが投資が先行して売り上げが追いつかないケースだ。きちんと財務情報を開示しているか、流動性は確保されているか、売り先の顧客が分散されているかなど定性的要素にまで踏み込んで見る必要がある。大企業の場合であれば、利益率の改善・自己資本変化率など中小企業とは違った観点から評価する。
エコビジネスを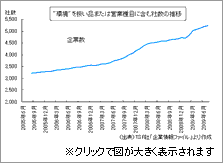 手がけている企業が増えている。社会的注目も集め景気のけん引役として期待されている。
手がけている企業が増えている。社会的注目も集め景気のけん引役として期待されている。
広告減収の中、エコ関係の広告だけは底堅いとも耳にした。トヨタ自動車がハイブリッドカーに向かうなど既存企業の転進が主体であり、ITバブルの時のような新興企業の登場とは異なる印象をもっている。ただ定量的な評価にはもう少し時間がかかる。
また地方分権、地域産業の振興について関心をもっている。
これまで地方経済=低成長・低リスクだったが、地域経済の成長性が高まればその分リスクも出てくることになるからだ。地域振興は地域リスク管理の必要性を呼び起こすだろう。
さらに、国際会計基準の動向にも興味がある。日本企業の国際会計基準への対応という面ばかりでなく、逆に、海外企業を同じ会計のモノサシで見られるというメリットもある。先進国企業ばかりでなく最近は新興国の企業も成長しており、今後、日本企業に対する海外企業からのM&Aもありえるので、国際会計基準を通じた海外企業の評価にも目を向けているところだ。
信用リスクという観点からは、不況時の定番だが、自己資本にみられる健全性と、流動性(運転資金など)の確保の2点に注目すべきだろう。中小企業の場合、金融機関の態度から影響を受けにくい財務体質を築けているか、また実態を正しく反映した財務の開示ができているかが重要な点となってくる。