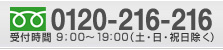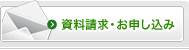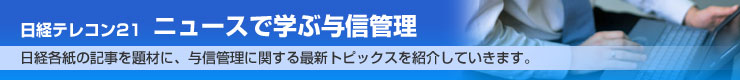日経テレコン21ビジネスセミナーでもおなじみの与信管理コンサルタント・牧野和彦氏が、日経各紙の記事を題材に与信管理の最新トピックスをご紹介します。日経テレコン21をご契約の方は、題材となった関連記事の検索・表示が可能です。
解説:減少する上場企業数
上場企業数が3年連続で減少しています。20010年3月末時点では3,704社となり、2009年度末より114社も減りました。また、ピークだった2006年度末からは、222社と6%の減少となりました。
要因は、三つ考えられます。
一つは、ここ数年は上場企業の倒産が多かったことです。
二つ目は、企業統治や戦略の観点から上場子会社を上場廃止にして、自社内に取り込む親会社が増えたことです。
三つ目は、IPOが19社と低水準に留まったことです。
特に興味深いのが、一つ目のポイントです。2008年度は45社という戦後最多の上場企業の倒産がありました。その結果、上場企業の倒産率もかつてないほど上昇しました。
●上場企業の倒産率
45÷3,818×100=1.18%
●法人全体の倒産率 ※財務省「法人企業統計調査」2008年度
16,146÷2,822,497=0.57%
実に、法人全体の倒産率の2倍だったことが分かります。
もちろん、これは2008年度だけのことです。2009年度の上場企業の倒産は7社でしたから、倒産率は、0.19%となり、法人全体の3分の1程度の倒産率になります。参考までに、上場企業の倒産は、2006年度は3社、2007年度が7社となって います。
一時的にせよ、こうして上場企業の倒産率が上がるということは、与信管理を行う上で大切な気づきを与えてくれます。
「上場企業だから安心」という時代は終わりました。もちろん、依然、上場していれば、ある程度は信頼できます。しかし、全ての上場企業が財務的に安全とは限りません。これからは、上場、非上場以外の別の判断基準を持つ必要性があります。
解説:増加する倒産防止共済の加入企業
「中小企業倒産防止共済」の加入企業が増加しています。2009年度は、2月までの時点で27,000件を超えており、1998年度以来、実に12年ぶりの高水準です。
「中小企業倒産防止共済」は、中小企業が毎月掛け金を積み立てておき、取引先の倒産で売上債権が回収不能になった場合、回収不能債権額相当を無担保、無利子で借りることができます。
借り入れを受けずに40ヶ月経過すると、共済の脱退時に掛け金の全額が返還されます。加入企業が増える一方では、資金繰りのために、脱退して掛け金の返還を受ける企業も出ています。
ただし、取引先が倒産して、実際に貸し付けを受けた件数は、2008年の5,391件から2009年は2月までで3,898件と大幅に減少しています。全国の企業倒産件数減少の影響が如実に表れていると言えます。
解説:海外向け債権を担保に融資
日本貿易保険(NEXI)と商工組合中央金庫は、保険が付保された中小企業の海外向け債権を担保に優遇金利で貸し出す仕組みを開始します。
NEXIの貿易保険が付保された海外向け債権は、バイヤーの破たんなどによる信用危険、相手国における戦争や災害の勃発による非常危険などが保険によりカバーされています。
商工中金にすれば、保険付きの債権は国が支払を保証しているようなもので、確実な担保になります。貸し出しに伴う信用リスクが抑えられているため、金利を下げることが可能になります。
輸出を行う中小企業に取っては、通常の貿易保険では、保険金が支払われた後も、輸出者に回収義務が課せられるところを、このスキームではNEXIが回収を行うため、業務負担が軽減されます。
NEXIにすれば、商工中金の貸付先への貿易保険の販路拡大になります。このスキームは、政府の緊急経済対策における中小企業の資金繰り支援策の一環です。
自国内での市場が飽和状態にある日本企業にとって、輸出の拡大や海外進出は緊喫の課題です。貿易保険は民間の損保会社も提供しており、NEXIだけを国が支援するのは民業圧迫ともいえますが、資金調達手段の多様化は中小企業にとっては朗報です。
解説:3件に1件は承認、返済条件の変更
大手銀行は昨年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」に基づく返済条件の緩和実績を発表しました。実績は1月末時点でのものです。
法人と個人全体の申込件数は36,940件で、条件変更に応じたのが11,558件でした。比率にすると31%となり、10件中3件は返済条件変更が認められた形になります。
内訳を見ると、法人からの申し込みが29,480件。そのうち条件変更に応じたのは10,664件でした。比率は36%で、3件に1件は認められた形です。
法人の条件変更の申し込みが一番多かったのが、三井住友銀行で10,236件、次いで三菱東京UFJ銀行の9,268件、みずほ銀行の6,229件、りそな銀行の3,747件となっています。
承認率では、りそな銀行が最も高く46%でした。次いで、みずほ銀行の44%、この2行では半数近くの条件変更に応じていることになります。そして、三菱東京UFJ銀行の34%、三井住友銀行の29%の順となっています。
ただし、承認率の高さは、申込件数の多さと全く反対になっており、条件変更の依頼が多いほど、リスクの高い融資先が混じる可能性が高いとも考えられます。
一方、東京商工リサーチが発表した2月の全国法人倒産件数は、1,090件で、前年対比17.2%の大幅な減少を記録しています。各月の倒産件数が前年を下回るのは、これで7ヶ月連続です。
一種の延命措置とも言える返済条件の緩和措置ですが、7ヶ月連続で減少し続ける企業倒産件数を見る限りでは、一定の効果は出ているといえます。
解説:激減する手形交換
平成21年の手形交換枚数は9621万枚となり、初めて1億枚を下回りました。
同年の手形交換高は、373兆5300億円となり、前年対比で13.7%の減少となりました。
また、不渡手形件数は151,298件で、13%の減少。6ヶ月以内に2回の不渡りを出した企業に課せられる取引停止処分件数は、512,41件で、19.7%の大幅な減少となりました。
10年前の平成11年には、2億3千枚だった手形の交換枚数が半分以下に激減したわけです。手形の交換高にいたっては、千兆を超えていたものが、6割以上減りました。
企業間決済において、約束手形による支払を選択する企業が減ったことが大きな要因として挙げられます。
これは、手形に貼る印紙代を始めとした手形管理のコストを嫌気する企業が増えたこと、不渡りになった場合の倒産リスクがある手形決済を避ける企業が増えたことなどがその理由です。
また最近では、電子債権の登場も見逃せない要因です。
昨年7月末には、三菱東京UFJ銀行傘下の日本電子債権機構が営業を開始し、三井住友銀行、みずほ銀行もそれぞれ子会社を設立し、追随する見通しです。
また、全銀協が平成24年5月に開業予定の「でんさいネット」には、全国の銀行や地銀124行、信用金庫、信用組合など1188の金融機関が参加予定となっています。
こうした電子債権が今後普及してくると、紙の手形の減少に拍車がかかるのは必至です。
解説:サービサーへの監督強化
法務省は4月からサービサーへの監督を強化する方針です。
サービサー法が施行されてから10年が経過しましたが、債務者に対する強制的な取り立てが増加傾向にあると民主党は見ており、具体的な禁止行為や罰則を明示します。
実際、サービサーへの行政処分は2009年に6件と過去最多となりました。具体的に禁止される行為としては、下記の例示が検討されています。
(1)保険金やその解約金を債務弁済に充てるよう強要、示唆しない。
(2)正当な理由なしに債務者の勤務先に電話したり、FAX、電子メールを送信したりしない。
(3)債務者の自宅や勤務先などに支払を求めて居座る
(4)債務者以外の第三者が拒否しているにもかかわらず、取り立ての協力を要求する
今年、業務改善命令が下されたサービサーの場合は、主に書類関係での不備、過誤事例が発生しており、内部統制の十分な構築されていないことが指摘されています。
現在、法務省の許認可を受けているサービサーは101社となっており、2009年6月末における取扱債権の累計額は265兆円に達しています。
国民に優しい民主党としては、サービサーに限らず企業に対する規制を強化して、返済に苦しむ庶民の人気を取りたいのでしょう。しかし、過度な消費者保護は、借りたお金を返す、義務を履行するという意識が希薄になるモラルハザードにつながる懸念があります。
むしろ、規制を緩和して新規事業を生み出し、雇用を増やし経済成長につなげる発想こそが求められています。
解説:急増する奨学金の延滞
日本学生支援機構では、奨学金の延滞債権が急増しています。
同機構の平成21年度末における返還を要する債権額残高は3兆6,145億円で、 貸倒引当金は1200億円を計上しています。残高に対する比率は3.3%。
一般的な不良債権比率の目安とされる3%と単純には比較できませんが、これ だけ見るとすごく悪い数字ではありません。
一方、3月以上の延滞債権は2,386億円であり、要返還債権に対する割合は6.6%、 6月以上の延滞債権は1,901億円、割合は5.3%となっています。
一般的なエイジングで見た場合、3ヶ月、つまり90日以上の遅延債権の売掛残 高に占める割合の目安は0.1~1%と言われています。
それに比べると、同機構の5~6%という数字はかなり大きいことが分かります。 さらに、件数(人員数)で見るとこの比率は更に悪化します。
同時期での返還を要する人員242万3千人のうち12.8%の31万人が返済を滞 納しており、未返還は20.3%の723億円にも上っています。
貸付金の1割以上が遅延し、2割を回収できないというのは、民間では考えら れません。2割の不良債権は連鎖倒産の可能性さえあります。
同機構では平成20年度に、1年以上の延滞債務者29,075件に対して支払督促 申立予告書を発送、2,173件に対しては「支払督促申立」を行い、867件に対 しては「仮執行宣言付支払督促申立」を行っています。
さらに、債務名義を取得した853件に対しては「強制執行予告」を行い、19 件に対して「強制執行申立」を行いました。
気になるのは、支払督促申立予告書を29,075件に発送したのに、支払督促申 立をしたのはわずか2,173件しかなかったことです。比率にして10分の1に も及びません。
残りの9割は法的手段に驚き、実際に返済をしたのか、あるいは返済の意思を 示したのかは分かりません。いずれにしても、支払督促を示唆する有効性を考 える上で大いに参考になります。
また、サービサーへ委託した債権の回収率の高さも興味深いです。回収件数が 46.8%、金額ベースで23.8%となっています。1年以上の延滞債権は一般的に は2割も回収できない中、件数にして半数近くが回収できるということは、驚 異的とも言えます。
この当たりに、同機構の与信管理、債権回収体制の改善点が垣間見えそうです。
※このページに掲載しているコラムは、牧野和彦氏のメールマガジン「<クレジット&コレクション>■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■」より、著者の許諾を得て抜粋・転載したものです。

ナレッジマネジメントジャパン株式会社 代表取締役 / 与信管理コンサルタント
早稲田大学卒。ダンアンドブラッドストリートジャパンを経て、2000年に現在の会社を設立。与信管理のコンサルティングや講演、執筆業務を行う。与信管理、債権回収、財務分析、海外取引などをテーマに過去450回の講演をこなし、受講者数は12, 000名を超える。早稲田大学、SMBCコンサルティング、東京商工会議所、JETROの講師としても活動中。